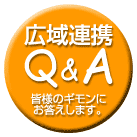 |
Q1 どう生まれ変わるの? |
| A1 県下102の商工会が、22のグループに分かれ、それぞれ広域連携協議会を設立しました。広域連携協議会では、会員事業所の皆様に、より高度で専門的なサービスを提供する事をモットーにしています。 |
|
Q2
|
広域連携体制はどんなもの? |
|
A2
|
広域連携協議会は、いくつかの商工会が互いに協力・連携しあうなかで、拠点となる商工会(幹事商工会=当協議会は塙町商工会)に事務局を設置します。
協議会事務局には幹事事務局長と広域担当経営指導員を設置し、連携する商工会の区域を管内として、高度で専門的なサービスにあたります。
一方、商工会には、従来通りの基礎的な経営改善普及事業を担当する地区担当経営指導員を配置しますので、会員事業の皆様は「従来の商工会」と「広域の商工会」の両方から支援・指導をうけることができます。 |
|
Q3
|
なぜ広域連携体制がもとめられるの? |
|
A3
|
近年、商工会組織の基盤である小規模事業者・会員数は年々減少しています。この状況下において、商工会組織が現状を維持することは、非効率的であると言えます。
また、会員事業所が求めるサービスにも、高度化・多様化の傾向が見られ、現状の組織体制では対応できないようなニーズも生じてきています。
これらの課題に対応するには、限られた人的資源を高度専門的な知識を持つ人材に育成し、幾つかの商工会を広域的に活動させることが効率的かつ有効です。広域連携体制ではこれらの事を実現させます。
|
|
Q4
|
協議会事務局の職員は誰がなるの? |
|
A4
|
協議会事務局の幹事事務局長は、幹事商工会の事務局長が兼務します。
広域担当経営指導員は、地区担当経営指導員と広域連携経営指導員を兼務します(単会拠点常駐併用型)。
広域担当経営指導員については、高度で専門的な支援に対応できるだけの能力向上を図ります。また、商工会の従来の会員サービスを充実させるため、補助員が経営指導員の職務を実施できるように、能力向上を図ります。 |
|
Q5
|
会員サービスはかわるのか? |
|
A5
|
商工会は、従来どおりの金融・税務記帳等のサービスを提供します。
さらに、広域連携協議会からは、高度・専門的なサービスを提供します。会員事業所の皆様は「従来の商工会」と「広域の商工会」の両方からサービスをうけられます。 |
|
Q6
|
高度で専門的な支援て何? |
|
A6
|
主に、国の重点事業である創業支援・経営革新支援のことです。特に経営革新支援においては、経営革新ビジネスプラン提案事業、ISO認証取得支援事業、リスクマネジメント支援事業など、具体的な事業を実施するほか、従来の商工会体制では対応することが困難な高度な相談についても、広域担当経営指導員が対応することになります。
これらの会員サービスを充実させるためにも、県連合会は研修体系を充実させ、広域担当経営指導員の能力向上に努めております。
|
|
|
|